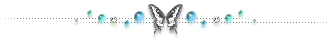|
白一色で統一された病室にフルーツナイフが規則的に実と皮を分け剥いていく音がしょりしょりと心地良く響いている。 日番谷はぼんやりと自分の無骨な両手が器用に林檎とナイフを操っている様子を見つめ、ふとその手を止めた。 「たい、ちょ…」 彼が動きを止めるのを待っていたように、微かな声が無機質なベッドの中から聞こえる。 は自分の視界が歪んでいるのに少し戸惑いながらも、目が覚めて真っ先に感じた霊圧が日番谷のものであったことに心底安心した。 「身体中が、痛い、です」 「当然だ。死んでねぇだけありがたかったと思え」 途切れ途切れに、自分が言葉を発していることを確かめながら白い天井に向かって話しかけると彼の憮然とした溜息が返ってきた。 再び再開されたしょりしょりと規則的な音に、彼女はくすりと微笑んだ。なんだか重症患者にでもなったみたいだ。 実際に彼女の負った傷は重傷と呼ぶに相応しいものであるのだが、こうしてしっかりした意識の元にあるとそんな風には感じないから不思議だ。 の能天気ともとれる笑顔を一瞥した日番谷は剥き終わった林檎を等分に切り分け、ひとつひとつ芯を取っていく。 「林檎、好きです」 はぎしりと悲鳴をあげる身体を叱咤しながら、どうにか首だけを枕元の椅子に腰掛ける日番谷へと巡らす。 小さなサイドテーブルに置かれた皿に、剥かれた赤く艶やかな林檎の皮が重なっている。その几帳面に均一な様子に“日番谷隊長らしいな”と、再びくすりと鼻笑みをこぼす。 日番谷は布団からちらりと覗いた彼女の首筋に巻かれた包帯の薄気味悪い程の白さから目を逸らすように瞼を伏せると、「松本からだ」と簡潔に告げる。 「乱菊さん、ですか」 「今回の件は松本の不注意も大いに関係ある。合わせる顔がねぇとか、結構塞いでたぞ」 かたりとフルーツナイフを置くと、八等分した林檎をひとつ摘まんでの口元へ寄せる。 しかし彼女の意識は今し方の日番谷の言葉へと注がれていて、目の前の瑞々しい果実にまで気がまわらない。 「そんな、単に私が弱いだけ、なのに」 「それは言うまでもない事だ」 彼女の心許無い物言いをばっさりと切り捨てた日番谷は、 の口元へと差し出した林檎を自らの口へと運ぶ。 かしょ、と軽快な音がして林檎の甘い香りが室内に満ちる。 は無言で林檎を咀嚼する日番谷を見つめ、少し不機嫌に眉根を寄せる。 「ひとりで食べると、美味しい、ですか」 日番谷は彼女にしては珍しい、拗ねたような表情をひとしきり眺めてから微かに口角を上げて笑った。 「普通」 言いながら椅子から立ち上がると、汗で少し湿った彼女の前髪を梳き混ぜるように乱暴に撫でた。が何か言う前に「残りは後で食べろ」と言い置き、足早に病室を後にする。 ぱたりと控えめに閉じられた扉の音を機会に、はゆっくりと瞼を閉じた。 彼が触れた前髪に林檎の甘酸っぱい移り香が満ちて このまま眠りに落ちたら良い夢が見られそうな気がしている。 |
林檎の魅惑的な眠り
(20080218 / copyright coma / title from ontology)