「雪?」
そう問いかえす日番谷の口調はどこか、気もそぞろだった。
窓の外は、すっかり夜の帳が下りて真っ暗。
今夜は天気も崩れると聞いていたし、寒さも増している、早く帰宅したほうがいい
そんな思いも込めて、使っていた史料を手早くまとめて順に並べる。
書庫は、天候の不安定か気候の寒さからかはわからなかったが二人以外は誰も残っていない、
それが余計に寒々しさを増す。
この冬に下ろしたばかりの着物の真新しい匂いが冷たい空気に触れて鼻をつく、
それは墨の匂いに似ている。
まるで春に新人として任命された時のよう、もう半年以上も経ち、
仕事もそつなくこなしている彼にとっては、久々の感覚だった。
>br> 「降り始め、って意味スか?」
問い返すのは、同じ隊の席官のに対して。
日番谷よりも十年以上早く死神をこなしている先輩のは、穏やかで落ち着きのある女性だった。
だが、たかが十年、寿命がないに等しい自分達では彼女は若い方、つまり出世が早く実力があるということ、
そして落ち着き方もどこか他の死神よりも成熟しているように思えた。
そして日番谷はといえば、実力も仕事ぶりも入隊時からすでに先輩席官を凌ぐほどで、
あとは多少の経験があれば直ぐに隊長格に昇格だろうと示唆されていた。
そんな鳴り物入りの入隊を果たした自分にあてがわれたのは彼女で、最初はそんなものかと思っていた。
つまり年数が近くて、おまけに全てにおいて出来のよい先輩を教育係としてあてがってくれたのだろう、
そんな程度にしか思っていなかった。
話はそんな単純でもなかった、というのは、つい最近になって知った話。
「うーん、そうとも言えるし。そうじゃないとも言えるかな」
愛想がないと言われ続けた自分だが、手早く片づけをしながらも、
一応律儀に返事をするのは性格だった。
「なんすか…それ」
が背を向けて日番谷が並べた順から本棚につめていくのを
ようやくそちらに目を向けて尋ねたのは、質問の意図を知りたかったから。
「だから----生まれるところ、って意味」
なんだそりゃ。
そういいかけて、けれど黙る。
は、頭のいい女性だった。
それは日番谷も認めている、学院にいたときには自分以上の人物なんていなかったのに、
入ってみたら、まず一番身近な人間が自分よりも頭がよかった。
だから、彼女の発言は無下にはしない。
だが…その内容が突拍子のないものである時があるのも…知っていた。
「…」
問う前に考えるのは彼の性格…、けれどもともとの自分の思考回路にないものは、
解答が得られるはずがない。
そして、その解答が彼女特有のものであることも知っていた。
これはその典型的な例。
絶対そうだ。
だから、背を向けている彼女に質問の方向を変えてみた。
「見たいんすか?」
最後の方は、背が届かないらしい。
精一杯背伸びをして書棚に史料を突っ込もうとしているの背を見つめる。
(…無理だろ)
かなりの蔵書率を誇る瀞霊廷の書庫。
つまり天井までぎっしりと詰まれて、歴史も誇っているものだが、
となるとその積み込まれ具合には隙が無い。
そっと目をやれば、取るときに使ったはしごは、書棚の奥の方。
横着をせずにそれを動かせばいいのだが、そういう気にはなれないのは
日番谷も同じだった。
たまに、彼女が横着なのは愛嬌なのか。
頭がいいくせに、そういうことをする。
そしてその結果は…わかっている。
溜め息を一つこぼし、近づく。
の手で無理やり隙間に詰め込もうとされたそれは、不安定に定まらない。
このままじゃ、入らない。
それどころか、そのとなりの斜めになった本が崩れてくる。
「おい」
「え…きゃあ!!」
に声をかけ、彼女が振り返ろうとした瞬間、その肩に手を置き
弾みをつけて空中へ飛び上がる。
そして棚の桟に足をかけて、驚く彼女の手から本を抜き取り、
斜めの本を直しつつそれを書棚の隙間に埋め込んだ。
その間、わずか数秒。
綺麗に全てを片付けて、日番谷ははずみをつけて足を離す。
「…よし、と」
とん、っと足音さえたてずに地面に着地した日番谷は
床の上にしりもちをついていたを見下ろし不審そうな顔をする。
「なんだ?」
「…なんだ、じゃないよ!」
「そんな体重かけてないけど」
このくらいで死神が情けない、と思えば
は悔しそうに頬を赤らめた。
「そうじゃないの、びっくりしたの!」
「わかったってば」
だって、仕方ないじゃないか。
自分がより背が高ければ…あの棚に届くくらいの背丈があれば
別に弾みをつける必要なんてなかったのだ。
それよりも、睨みあげてくる彼女がいつもよりも幼く見える。
彼女が気がつかない程の小さな溜め息をこぼし、目を逸らしてしまったが
気を取り直して、意識して彼女を見下ろす。
少し不満げな顔は、機嫌を直していない。
「…ん」
驚きに見開いた目が嬉しそうに笑って掌に暖かさが加わる、それを引っ張れば満面の笑みがあった。
立ち上がったが袴を払う、丁寧に手を添えて屈みこみそっと埃を落とす姿、
その所作に目を止めた。
白い手首に目が奪われた。
「…」
いつも余裕で大人びた日番谷と仕事をこなす、だがたまに見せる女の部分に
気まずくなることがあった、目のやり場に困る。
微かに触れた体温は、すぐに消えた。
離れた手には、消えて行く温もり。
その片鱗を忘れたくなくて、掌をぎゅっと握った。
「そういえば、さっきの話…」
出来上がった書類を日番谷が持ちが明かりを消す。
暗くなった室内の戸を閉め、施錠を確認したに尋ねた日番谷を振り返る顔。
「なあに?」
「だから、さっきの雪の話だけど」
自分で言ったくせに、そう告げれば、なんとなくしんみりとは言った。
「私ね、瀞霊廷に入って初めて雪を見たの。南流魂街の出身だから」
「ふーん」
「雪って不思議よね」
少しだけ口元を緩めて楽しそうに笑う、その後ろを歩くのは悪くない。
「目覚めるといつも真っ白でしょ。いつの間に積もったのかなって。
だからいつも確認したくて、起きているのだけど」
「…そんで、いつも遅刻するんだ」
ボソリと呟くと、顔を真っ赤には反論した。
「ち、違うよ!!」
「それで雪の日は遅いのか…」
いつもはちゃんと時間通りのが、なぜか冬になると遅い日がある。
ただ単に天候が悪いからか、と思っていたけれど。
初めて知った彼女の意外な部分に、ついもっと触れずにはいられなかった。
「ちがうよ!!別にちょっと見ていたら…」
「寝過ごすんスね」
違うってば、そう言うを追い抜く。
その背につん、と引き戻される感触…それに足を止めた。
肩を引く感触、服の裾ではなく肩をそぅっと触れるのは彼女の呼び方。
「ねぇ、ちょっとだけ…見ていかない?」
「…?」
「…雪の生まれる瞬間」
そう言って、は笑った。
「本当に降るのかよ…」
「それは、冬獅郎のほうが知ってるでしょ」
は、入隊当時からなぜか日番谷を冬獅郎と呼ぶ。
異例の席官入りの入隊を果たし、どこか遠巻きに見られていた自分へ親しみを込めて呼びかけられたそれは、最初は驚きもあったが慣れれば心地いいものとなった。
それが、の気遣いだと鈍い自分はようやく知ったのだ。
「…別に俺は、予報ができるわけじゃないし」
冷気の霊圧を放ち、氷・雪系の鬼道が得意な日番谷を指しては言う。
「…じゃあ何ができるの?」
そう尋ねられれば、困ってしまう。
雪が降らせられる、そう言えるにはまだ早い。
方法もなんとなくわかる、けど微細な制御がやったことがないから面倒そう。
だから、即答はできなかった。
黙ってしまう日番谷に、は小さく笑って、そして体を寄せた。
「…」
隊舎の屋根はとんでもなく寒かった。
そこに毛布を持ち出し包まって雪を待つなんて正気じゃない。
けれど…。
「寒いね…ねぇ。一緒に入ったほうがあったかくない?」
「…え」
何をするのか、と思えばが毛布を広げて日番谷の肩にかける。
そして身を寄せてきた。
「…お、おい?!」
「だって一人一枚で包まるより、二人で二枚に包まる方があったかい」
無邪気に寄せてくる身体、その冷えた肩が少し震えていた。
寒いのだと、直ぐにわかるけれど。
その細い肩は、近くで見ると思った以上に華奢だった。
「…」
迷い、そしてそっと動く。
あまり彼女に触れないようにと気をつける。
日番谷がの要望どおりに毛布を広げると、笑みをもらして
その中にが入ってくる。
二人で二重に包まると、確かに暖かい気がした。
の匂いが、温められて鼻腔をくすぐった気がした。
一気に縮まった距離、願っていたはずなのに
急に叶えられてしまうと、いつもよりも鼓動が早い気がする。
「…これ、凍死すんじゃねぇのか?」
「冬獅郎が?」
「いや、が」
まさか氷系の能力の自分が、凍死するとは思えない。
けど寒いもんは寒い。
このまま一晩夜を明かすなんて、不可能だ。
「なんで?冬獅郎は平気なの?」
「俺は、凍死はしないし」
「じゃあ、私もしないよ。冬獅郎がいるもん」
まさか、見捨てはしないでしょ。そう言って触れる肩に、胸が躍るのはなぜか。
自分はどうしたいのか、わからなくなってくる。
「…いつまでいるんだ?」
「雪が、降るまで」
結局、問いは最初に戻る。
降るのか、という問いかけは飲みこんだ。
「目が覚めたら、真っ白だったら素敵だね」
「その前に目が覚めねぇだろ。俺らが凍る」
毛布の中で、の手が、日番谷の手をキュッと握る。
鼓動が…早い。
どうして…こんなふうに触れてくるのか。
たぶん、といて初めてかもしれない、こんなにうろたえているのは。
いつも落ち着きすぎていると言われて、初めての任務でも難しい任務でも淡々とこなす
自分を、指導者泣かせだとは口を尖らせて抗議していたから。
「…」
肩を抱こうかと逡巡していた日番谷の悩みを
あっという間には飛び越えてくる。
重ねた手が熱い。
「いいよ…冬獅郎と一緒なら」
「…」
その質問の意図は…問うことはできなかった。
「このままずっと、ここにいたい」
肩に重みがかかる、冷えた肩、髪が日番谷の頬を掠めた。
繋ぐ手は温かい。
その願いは、日番谷こそ思うものだった。
ずっとこのままで…いられたらいい。
けれど、それを口にすることはできない。
鳴り物入りの席官。
天才児と言われる自分を、最初は餓鬼が、と鍛えなおそうと大部分の席官が
息巻いていたのだと言う。
だが、いつのまにかそれは自分の知らないところで無くなっていた。
新入りの制裁でさえも、躊躇されてしまう自分。
----相変わらず自分は異端だった。
自分と関わるのを避ける死神達のなかで、唯一だけが最初から最後まで積極的に接していてくれたのだ。
(…は)
の能力はすごいと思う。
頭もいいし、強い。
それは、自分が認めてしまうほどの実力。
他人を認め、他人に認めさせてしまう。
(…俺は)
後輩の自分は、まだに届かない。
性格が明るくて積極的なは、上からの受けもいい。
同期の男と仲良くしていると聞いた、上位席官から言い寄られているとも聞いた。
「冬獅郎は、まだまだ私を追い抜いちゃ駄目だよ」
「…」
「まだ、ここにいてね」
いつになれば、一人前と見てくれるのか。
無邪気に握る手、肩に乗ってくる頭の重み。
いつになれば一人の男としてみてくれるのか、それは…まだ自分にはわからなかった。
***
「雪、降りそうだね」
が、窓の外を見て日番谷に知らせた。
温かな茶を指で包んで、つられて日番谷もそちらへと目を向けた。
死覇装をまとう黒い姿が日番谷の傍に並んでいる。
「…そうか?」
「すごく寒いもの」
「降ってほしいのか?」
「そうだね」
雪を待つ口ぶりに思い出すのは、雪がみたいと言ったあの時の顔。
結局、お前は雪の生まれるところを見たのか?
そう尋ねかけた口を閉ざす。
「今日は早く切り上げていいぞ」
「…いいですよ」
あの時、結局雪は降らなかった。
あれから長い年月を得て、何度も瀞霊廷は雪に包まれている。
けれどは、まだ雪の生まれるところを見ていないのだろか。
再会したは、以前と変わりない顔で笑い、日番谷を冬獅郎と呼んだ。
互いに席位を上げていった今も、変わりない態度。
けれど…数日後は…。
小さな溜め息は、どちらがこぼしたものか。
まるで同調のように、それぞれではなく空気がこぼしたかのようだった。
が書類をくぐる音だけが響く。
そして自分は何とはなしに、ゆるく暖かさを伝えてくる湯飲みを掌で包んでいるだけ。
----近いうちに、自分は十番隊に行く。
隊長として、十番隊の長になる。
目出度い話なのに、それは互いの口から一言も漏れなかった。
いや、実際には日番谷にはあまりめでたいとも思えなかった。
…当たり前の、いずれ持ってこられる話だというのは入隊当初、
いやそれこそ学院にいるころから示唆されていたのだから。
「…急ぎのものもないだろう」
「けど、急いで帰ることもない」
の口調は、素っ気なく取り付く島もない。
それは上司である日番谷に対して不敬であったが、この隊にはのほうが長く、
死神としてもが先輩。
だから、日番谷もこだわることはなかった。
------日番谷は今、隊長付きとして一番隊にいて、今のは一番隊の三席だ。
副隊長でもないのに、隊長補佐。それは微妙な立場だが、周知にはその立場だけで
あぁと納得させてしまうほど、日番谷は特殊だった。
各隊の隊長について研修のように経験を積んだのは、まさに隊長になるのを前提としてのもの。
本来であれば副隊長で経験を積み、時期をみて隊長に任命されるものだというのに、
副隊長を飛び越えていきなり隊長になってしまうのは、まさに異例。
期待の星、いずれ総隊長としてあとを継がせるのではないか、そんな噂も飛び交うほど
特殊な扱いだった。
だが、それほど日番谷の能力が飛びぬけているのともいえ、また瀞霊廷が実力主義だというのを表していた。
「雪が降りそうだからって、早退していたら仕事が進みません」
「…雪が降ったら遅刻してくるくせに、か?」
席官の詰所には二人きりだというのに、どこか今日の彼女は気もそぞろでそっけない。
中途半端なの敬語は、日番谷がよりも命じる立場になってしまったから。
けれど、それを差し引いても、どこか触れ腐れたような口調は、彼女の言動にも表れていた。
今、を感じ取れるのは、彼女が入れたお茶ぐらいだった。
「知ってるんですか?」
「さぁな」
言えば、目を書類に戻し項をくぐるの手が止まった。
ここでと再会してから、まだ雪は降ってない。
だから、そのクセは治ったのかは確認していない。
けれど、きっと治ってないといいと思った。
後残りわずかだが、その顔は見られるのだろうか。
…雪にはしゃぐ、その顔を。
「けど…明日、降っていたら遅れてもいいぞ」
「…珍しいですね」
先ほどは遅刻を責めていたはずなのに。
ましてや、仕事に関しては滅多な理由では、サボることを許さない日番谷がと
わずかに意外のニュアンスをこめてが呟く。
雪のせいで遅刻なんて、絶対許さないと思うのに。
「まぁな」
日番谷の本当かどうかわからない軽口には、乗ることができなかった。
それくらい今日のは、口も気分も重い。
わざと書類に没頭している振りをして、顔をあけずに会話をやり過ごす、なのに
帰ることもしないで残っているを日番谷はどう思っているのか。
だが反対に今日の日番谷は、他のことに気を取られているようで
どこか気もそぞろで、仕事も滞りがちで所在無げにしているだけだった。
「…今日はどうしたんですか?」
「…」
「何か…」
気にかかることでも、そういいかけては、口を閉ざした。
気にかかっているのは、自分も同じだ。
無言で日番谷は、その問いには答えなかった。
チラリと窓の外を見る。
天候のせいでか、外は薄闇の帳が落ち始めている。
日番谷はかたん、と席を立ち、窓際へと寄る。
外気との差で曇っていた窓を開けると、いきなりの冷気が部屋に飛び込んでくる。
そこから身を乗り出し、日番谷は外を見上げた。
「冬獅郎?」
何をしているの、と尋ねるの口調。
そちらをチラリと見て、日番谷はすたすたと向かってくる。
「冬獅郎?」
がもう一度尋ねる。
まだ仕事中の机、書類を持つ指はそのままで止まる。
日番谷はその腕をしっかりと掴んだ。
「ねぇ?」
二度目の問いかけは、今度こそ不審な思いを強くしていた。
何をしているのか、と顔も口も問いかけている。
不思議そうな若干を緊張が孕んだような視線で見上げてくるに、日番谷は口を開いた。
「来いよ。もう仕事になんねぇだろ」
「え?」
そのまま引きずるように椅子から下ろすと、は状況がわからないながらも
足を動かしついてくる。
「明日遅刻してもいい。代わりに、今晩付き合え」
「残業?」
あぁ、細い腕だと思う。
あの頃よりも、自分達はいくらかは姿形も変ったはずなのに、
むしろ彼女が華奢になっているのは、どうしてだろうか。
どうしてだか、より女になっていくのは、どうしてだろうか。
「命令?」
「そうだな」
いつのまにか、命令できる立場になっていた。
いや、そうしたいと願い、だからこそ上り詰めたのかもしれない。
窓をあげたままの、桟によいしょ、と足をかける。
驚くを足をかけたま振り返り、再度手を差し出す。
「…」
「どこへ…行くの?」
震える声で立ちすくむ。
それに伸ばした手だけで、是可否を求める。
「…」
指が掌に触れた、微かに震えたそれを掴む。
僅かに口元が緩んだ、笑みが漏れたのがわかった。
「見せてやるよ」
「何…を…!」
言いかけた言葉は、最後までは音にならなかった。
ぐいと手を引きながら、宙に身を踊らす。
息を飲んだ、その腕を引き次いで腰を支えた。
空中へと落ちながらその腰を引き寄せて抱いて、そして空へと飛び上がった。
「冬獅郎、寒い!!」
「…伏せてろ」
凍てつく冷気が頬を打つ。
氷の粒子を含んだ大気を鼻が感じる、冷たいつんとした匂い。
「伏せてろ、って…」
「お前は、俺に掴まってればいい」
腕を広げて、半身にの顔を埋めさせる。
外を見る必要はない、日番谷が上へと連れて行くのだから。
抵抗はなかったのは、寒さゆえか。
大人しく従う彼女にほっとした。
あと少し。
あと少しで、そこに行くから。
「目、開けていいぞ」
の腰を支えて、そっと囁く。
寒さで、吐く息が白いどころかそれさえも凍っていきそう。
彼女を支えるよりも、その体から伝わる熱に救われているのは、自分だった。
「ここは…」
「…寒いが、我慢してくれ」
雲の上は、月が綺麗に真ん丸だった。
左はの腰を、そして右手に氷輪丸を掲げる。
僅かに氷輪丸を左右にふると、リンと澄んだ音がした。
大気が更に冷えた。
「ねぇ…何をしているの?」
の声が震えているのは、寒さからか。
それとも別の理由があるのか…それはわからない。
「…」
無言で、彼女を抱えたまま下へとすっと降りていく。
雲に身体が触れる、寒さと冷えた空気が体を包み込む。
そして、身体が雲を抜けた。
「…わぁ…」
その声で、制御がうまくいったのだとわかった。
灰色の空、雲ひとつでこんなに違うのかとも驚く。
「ねぇ、冬獅郎!もう少し下に降りて」
「あぁ」
いまや、冬獅郎の意図を知ったが注文をつける。
雲から生まれた雫が白い塊になる。
透明な糸が白い綿のような雪に生まれ変わり、落ちていく。
はらはら、しんしんと。
静かに、静かに、落ちていく。
「雪、見れたか?」
「…」
日番谷の力で、大気の温度を下げたのだ、もしかしたら下に落ちる頃には
溶けているかもしれないし、反対にこれから温度が下がれば更に降り積もるかもしれない。
「案外、あっけないものだな」
「…」
もっと爽快な風景かともおもったが、案外静かで自然なものだった。
けれど落ちていく雪を見下げているのは、初めて見る風景だった。
ただただ、静かに白いものが下へと落ちていく。
「もう少し、下」
「?…あぁ」
が日番谷の襟を引っ張る。
それに応じて、するすると少し降りる。
丁度雪が生まれたばかりの、そして落ちていく中に留まる。
が目を閉じる、その脇を抱えている自分。
宙に浮かんでいると、身長差などあまり感じないものだと思う。
「…ねぇ、上見て」
「あ、あぁ…」
言われて空を見上げれば、白い塊りが真上から視界を覆いつくすように
後から後から落ちてくる。
冷たい綿は、顔に触れると直ぐに雫となり冷たさだけが残る。
「生まれてる…」
「あぁ」
が目を閉じる、その顔で、体で雪を受け止めている。
その体が落ちぬように、そっと支えた。
「どうして、見せてくれたの?」
「…見たかったんだろ?」
ゆるゆると、の声も溶けるかのよう。
日番谷の胸に直接響く。
「…最後だから?」
「…」
「もう、行っちゃうから見せてくれたの?」
その言葉に、返事はできなかった。
「…行っちゃうのね」
そして、は静かに自分で答えを出した。
その響きに、寂しさがあったから…悲しみがあったから、言葉を口にできた。
「…俺が、いないと駄目か?」
「…」
今の隊で、同じになったのは、僅か半年だけのこと。
ずっと一番隊で席官をやってきたを抜いて突然やってきた俺の部下になって
そしてまた出て行く俺を、はどう思うのか。
文句もなく当たり前のように笑顔で迎えたは、また笑顔で送り出すかと思っていたのに。
「平気…」
は、呟いて下を向いた。
俯いた顔で、表情が隠れる。
「…平気だもの…」
それは、小さく消えていく声。
まるで雪のように溶けて、そしてしんしんと降り続ける雪の音だけが周りに残る。
その声は、まるで見捨てられた悲しみを含んでいるかのようだった。
「雪、見せてくれたから…もういい」
雪を見たからもういいのか?
それだけで、もう別れられるのか。
「あの晩…どうして、俺を選んだ?」
「…」
「どうして、一緒に雪を待ったんだ?」
「---覚えてない!」
無言のが日番谷を遮るように口をきる。
けれど、それが早すぎると思うのは、気のせいじゃない。
「覚えて…ないよ」
力なく言葉を紡いで、俯く顔に目を止める。
じっと見つめていると、その身体が震えていた。
「…ねぇ、離して」
「…」
「離してよ」
が身をよじり、ずっと支えていた日番谷の腕に手をかける、
もう一人で大丈夫だと言うように。
けれど…。
「嫌だ」
日番谷はそれを遮り、一層強く腕に力を込めた。
その言葉に、が驚いたように動きを止める。
「俺は…にとって、何だ?後輩か?それとも今度は上司か?いつまで、こうしていればいい?
いつになったら…こうして抱かせてくれるんだ?」
暴れるように背をむけていたの背中に顔を埋める。
その肩に話しかける。
息がかかるたび、言葉を一つ絞り出すたびに、の肩がびくりと揺れる。
華奢な背中の曲線がびくりと震えた。
「俺は…十番隊に行く」
そして、またの身体が揺れた。
「だから、お前も来い」
「なんで…」
「もう十分、待ったんだよ」
手をつなぎたいと、肩を抱きたいと思い願っても、それをすることができなかった過去。
はまだ先輩で、自分は後輩で。
の後ろにつき、そして自分は淡い思いを抱くだけだった。
けれど今は違う、叶えてほしいと言われた願いも叶えることができて、
に来いと命じることができる。
そのための、力だ。
「待ったって…」
「---嫌って言っても、連れて行く」
言えば、は口を閉ざした。
無理を通す、強い言葉で断言する。
そのために、俺はここまで来た。
「好きだったんだ」
「…」
「ずっと、好きだった」
返事は聞かなかった。
その顔を引き寄せて、後ろから唇を塞いだ。
柔らかな唇は、微かに震えていた。
ひんやりとしたそれを、冷えてしまったのだと思う。
温めるかのように、熱を与えるかのように覆い息を伝える。
思いを、ただ触れる唇に込める。
振りほどかない、抵抗しないに、期待を込める。
「…ずるい」
「…」
「そんなふうに言うのなんて…ずるい」
離した唇の先で、が吐息を震わせながら呟いた。
「惚れさせた、お前が悪い」
自分勝手な言い分。けれど、それは本音。
こんなふうに言うのも。
こんなふうに、手に入れたくなるのも、すべて…。
「…」
が目を潤ませて、呟く。
どうしたらいいの、と困ったように日番谷に縋るように唇を奮わせる。
「だから、お前も…惚れてくれ」
----それは願い。
片思いの数十年は、もう耐えられるものじゃない。
ただ、それに応えてくれればいい。
その背を引き寄せる。
己へと埋めさせるように、背を抱き寄せて
頬を両手で挟んで、唇を奪う。
断りがないのは、了承だと思ってもいいのだろうか。
顔を傾げて、何度も唇を重ねる。
唇に落ちた雪が解ける前に、そのまままた唇を重ねると、
冷たさと暖かさが混在する。
この熱で雪も解けてしまえばいい。
「…そんなの、もうとっくに-----」
重ねた唇の先で、漏らした言葉も封じた。
思いは、雪を待つ夜に生まれた。
そして、雪の中で思いは実を結んだ。
「…んっ…う」
の手が、日番谷の着物を掴んだ。
重なる唇、押さえつけるように食むと、
応えるように何度もの唇が喘いだ。
その感触を愛しいと思う。
応える唇に、ようやく追い抜かしたのだと、
認めさせたのだと、気持ちが高まる。
雪が上からも降り注ぎ、熱で溶けていく。
沢山の雪が生まれる中で、俺はへの思いを結んだ。
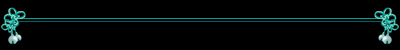
じゅんこさまへ。
今回は、じゅんこさんをイメージして「仕事」と「年上」をテーマになんとか書いてみました。
日番谷君は、入隊して年上女性と付き合ったに違いないと思っていたり。
けど短くて、説明不足な夢になってしまいました、ごめんなさい。
こんなものですが、貰ってくださったら嬉しいですv
さくらさま。
とても素敵な夢をありがとうございます。 さくらさまより、こんな素敵な夢をメールで頂いた時はもう、感激のあまり涙が。
私もこんなお話が書けるようになりたいです。
さくらさま。
本当にありがとうございます。